平日9:00-19:00
事前のご予約で夜間・休日相談可!
メール・LINEは24時間受付中!
まずはお気軽にお問い合わせください
045-900-6185
平日9:00-19:00
事前のご予約で夜間・休日相談可!
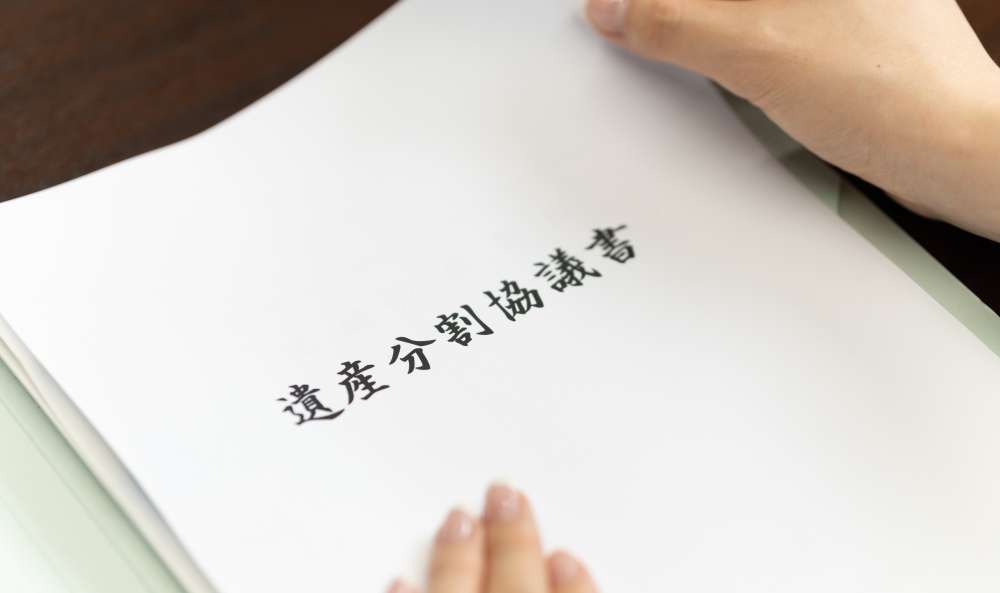
相続とは、故人が残した財産や権利、義務をその相続人が受け継ぐことを指します。一般的には、家や土地、預貯金、株式などの財産が対象となりますが、借金などの負債を受け継ぐ場合もあります。相続は、法律で決められた「法定相続人」とされる人々により行われるか、故人が生前に遺言書を作成していた場合、その遺言に基づき行われます。
相続の方法には、大きく分けて「法定相続」と「遺言による相続」があります。法定相続は、法律で定められた相続人が、決められた割合で財産を受け継ぐ方法です。一方、遺言による相続は、故人が生前に作成した遺言書の内容に基づき財産が分割されます。一般的に、遺言がある場合は、遺言の内容が優先されますが、法定相続人に与えられる権利である「遺留分」が侵害されている場合には異議を申し立てることが可能です。このように、法定相続人とは、法律上で認められている遺産を受け継ぐ権利を持つ人を指しますが、遺言による相続では、指定された人に財産が分配されるため、相続対象が異なる点にも注意が必要です。
配偶者は、法律で「常に法定相続人」とされており、他の相続人(例えば子供や親、兄弟姉妹)がいるかどうかに関わらず、必ず財産の一部を相続する権利を持ちます。これは、夫婦が共同で家庭を支え、財産形成に関与してきたと考えられるためです。また、配偶者は近親者の中でも特に故人と生活をともにしていた可能性が高く、今後の生活を保障するためにも法定相続人として優先的に位置づけられています。
遺産相続においては、法定相続人の範囲とその優先順位を正確に理解することが重要です。法定相続人とは、法律によって定められた相続の権利を持つ人のことを指します。法定相続人の中には、配偶者や子供、直系尊属、兄弟姉妹といった家族構成によって相続権を持つ人々が含まれます。本章では、それぞれの順位について詳しく解説します。
被相続人が亡くなった際、最優先で相続権を持つのが第1順位にあたる直系卑属です。直系卑属とは、被相続人の子供や孫など、下の世代に該当する人々を指します。法律上、子供がいる場合、全員が等しい権利を持って相続を行います。そして、もし子供が既に亡くなっている場合には、その子供、つまり孫が代わりに相続します。これを「代襲相続」と呼びます。例えば、被相続人に複数の子供がいる場合、それぞれが法定相続分を等しく分け合う形になります。
被相続人に子供や孫などの直系卑属がいない場合、第2順位として直系尊属が法定相続人になります。直系尊属とは、被相続人の親や祖父母を指します。この場合、もっとも近い世代の直系尊属、つまり通常は両親が優先して相続人になります。もし両親がともに亡くなっている場合は、さらに上の世代である祖父母が相続人となります。法定相続人とは、血縁関係に基づいて明確に順位が定められており、この段階で初めて直系尊属に相続権が移るのが特徴です。
被相続人に子供や直系尊属がいない場合、相続権は第3順位として被相続人の兄弟姉妹に移ります。兄弟姉妹が二人以上いる場合は、平等に法定相続分を分け合います。ただし、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供、つまり甥や姪が代襲相続を行います。しかし、甥姪のさらに子供に相続権が移ることはありません。兄弟姉妹が相続人となるケースは、第1順位や第2順位の相続人がいない場合に限定されるため、それほど頻繁には発生しませんが、分配の際には注意が必要です。
代襲相続とは、法定相続人が相続の開始前に既に亡くなっている場合に、その子供が代わりに相続権を引き継ぐ仕組みです。この制度は主に直系卑属に適用され、例えば被相続人の親が亡くなっている場合に孫が相続人となることがあります。また、兄弟姉妹が法定相続人の場合でも代襲相続は発生し、この場合は被相続人の甥や姪が対象となります。ただし、代襲相続が認められるのは1代限りとなりますので、甥や姪の子供がさらに相続権を持つことはありません。このルールを正確に理解することが、遺産分割のトラブルを防ぐためには非常に重要です。
配偶者と子供が相続人となる場合、法定相続割合は配偶者が2分の1、子供たちが残りの2分の1を平等に分け合う形になります。例えば、子供が2人いる場合、それぞれが4分の1ずつ相続します。このような配分は、子供が死亡した人の直系卑属であり法定相続人となるためです。この場合、配偶者は常に確保された権利を持ちつつ、子供たちのために相続財産を分けることになるため、公平性が保たれる仕組みとなっています。
配偶者と直系尊属である親が相続人になる場合、法定相続割合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。親は死亡した人の直系尊属にあたり、第2順位の法定相続人として相続権を持ちます。このケースでは、配偶者が生活を維持するための配慮として大きな割合が配偶者に割り当てられる一方で、親である直系尊属もある程度の保護を受ける形となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分配します。兄弟姉妹は死亡した人の第3順位の法定相続人であり、直系卑属や直系尊属がいない場合に初めて相続権を持ちます。また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子供(甥や姪)が代襲相続の対象となります。ただし、兄弟姉妹が法定相続人となる場合、相続割合自体が少ないため、遺産分割協議が必要になるケースが多いとされています。
法定相続分は、法律で定められた相続人ごとの財産分配の割合を指します。一方で、遺産分割協議では、法定相続分に基づく分割を原則としながらも、相続人全員が同意すれば自由な分割方法を選ぶことが可能です。たとえば、特定の不動産や資産を特定の相続人にまとめて分配する場合、全員の合意が必要です。また、遺産分割協議を円満に行うためには、相続人全員を戸籍謄本などで確認し、法定相続人とは何かをしっかり把握することが大切です。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停手続きを行うことも可能です。
遺留分とは、法定相続人に最低限保証される遺産取得の権利を指します。たとえ被相続人(亡くなった方)が遺言書で全財産を特定の人物に譲渡すると明記したとしても、遺留分を持つ相続人がその権利を主張すれば、遺留分相当分の遺産を取り戻すことができます。この制度は、法定相続人の生活を守るために設けられています。
法定相続人とは順位や範囲が法律で定められており、遺留分が認められるのは直系尊属や直系卑属などの血族相続人と配偶者です。兄弟姉妹には遺留分は認められないため注意が必要です。この特例に関する事前の理解が、トラブルの回避につながります。
相続手続きにおいて、法定相続人を正確に特定することは欠かせません。法定相続人とは、戸籍謄本を通して、被相続人の親族関係を遡ることで確認できます。特に、結婚や離婚、養子縁組などがあった場合、その全履歴をたどる必要があります。
また、被相続人に知られていない認知した子供が存在する場合や、異母兄弟の間で相続が発生するケースもあるため、戸籍謄本の確認を怠るとトラブルの原因となるため、法定相続人を正確に調査することが重要です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(資産と負債)をすべて受け継がない選択をすることです。相続放棄を行う手続きは家庭裁判所で行いますが、必ず相続の開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、自動的に遺産や負債を相続したとみなされてしまいます。そのため、相続の範囲や順位を正確に把握し、早めに判断することが大切です。相続放棄を選択した場合、その人は初めから法定相続人ではなかったものと扱われることを理解しておく必要があります。
未成年者が相続人に含まれる場合では、その法的手続きに特別代理人の選任が必要になることがあります。特に、親が相続人として利益相反する可能性がある場合、第三者が代理人として選ばれるケースが一般的です。
また、養子縁組が絡む場合、養子も法定相続人として認められるため相続順位に影響を及ぼします。同じく、複数の養子が存在する場合、それぞれが独立して相続権を持つため、遺産分割協議において注意が必要です。これらのケースでは早めのシュミレーションや専門家への相談が推奨されます。
遺産相続におけるトラブルの多くは、法定相続人間の意見の対立によるものです。これを防ぐために、被相続人が遺言書を事前に作成することが有効な方法です。遺言書を作成する際は、自筆証書遺言や公正証書遺言といった形式ごとの要件を満たすことが重要です。
一方で、遺言書を作成しても、法定相続人が持つ遺留分を侵害しない内容にする必要があります。また、配偶者や兄弟姉妹を含めた全法定相続人の立場を考慮した記載を行うことで、よりスムーズな相続を実現することができます。