平日9:00-19:00
事前のご予約で夜間・休日相談可!
メール・LINEは24時間受付中!
まずはお気軽にお問い合わせください
045-900-6185
平日9:00-19:00
事前のご予約で夜間・休日相談可!
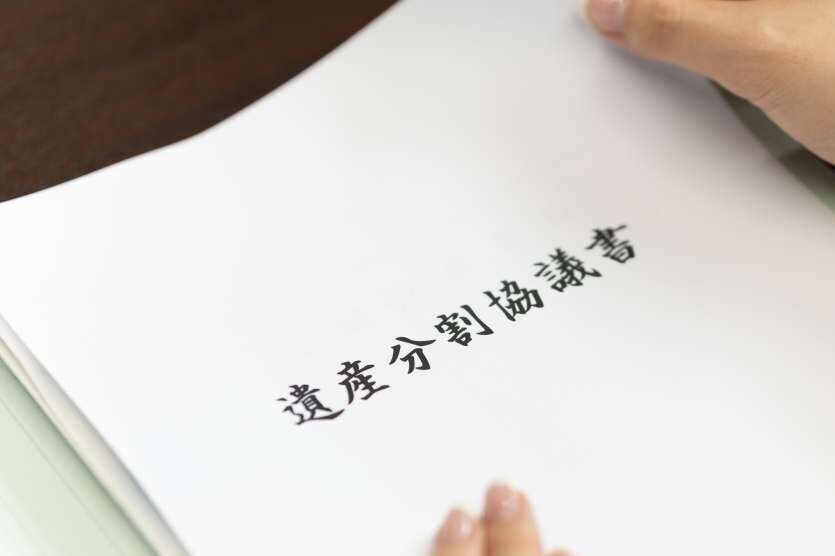
中小企業の自社株評価が必要になる場面として、代表的なのは相続や事業承継の際です。自社株は、上場株式と異なり市場での取引価格や時価が存在しないため、評価額を算定する方法が税法上で定められています。例えば、被相続人が中小企業の経営者で、その企業が持つ非上場の株式が遺産に含まれている場合、相続税を計算するために自社株の適正な評価が欠かせません。
また、自社株評価は相続時以外にも、事業承継を行う際、M&Aの検討時、あるいは株式の譲渡における適正価格算定のためにも必要となります。特に、中小企業の経営者が次世代へ経営を引き継ぐ際には、正確な自社株評価を行うことで承継の全体計画を立てやすくし、税負担を事前に見積もることが可能になります。
上場株式は証券市場での取引が行われているため、取引価格や時価が存在します。そのため、上場株式の評価額は市場価格を基準に簡単に算定できます。一方で、非上場株式、つまり中小企業の自社株については市場での公開価格がないため、評価額を算出するために独自の評価方法を用いる必要があります。
非上場株式の評価には、主に「純資産価額方式」「類似業種比準価額方式」「配当還元方式」といった方法が採用されます。中小企業は規模や条件に応じてこれらの方法を選択し、時には併用して評価が行われます。このプロセスは複雑であるため、専門知識を持った税理士や評価専門家の協力が不可欠です。
中小企業にとって、自社株評価は事業承継や相続の成功に直結する重要な課題です。自社株の適正な評価を行うことにより、相続税負担の予測が可能となり、必要以上の納税を防ぐ対策を講じることができます。また、事業承継時には後継者へのスムーズな引き継ぎが求められますが、自社株の評価額によっては相続税が重い負担となり、承継の支障となる場合もあります。
例えば、相続時に高額な自社株相続税評価額が算定された場合、納税資金の確保に苦しむケースがあります。そのため、生前に自社株評価の見直しを行い、早めに節税対策を検討することが推奨されます。税制の改正による影響もあるため、最新の規定について専門家と相談を重ねながら、戦略的に対応することが重要です。
純資産価額方式は、会社の総資産から負債を差し引いた純資産を基に評価する方法です。この方法は特に中小企業や非上場企業の自社株評価で用いられることが多く、会社の財務状況をそのまま反映します。
計算式としては、「総資産価額 – 負債価額」で純資産価額を求め、その後これを発行済株式数で割ることで1株当たりの価額を算出します。この方法は会社の純粋な資産価値を評価するため、業績や将来性の影響を受けにくいですが、不動産や有価証券などの「含み益」がある場合、それが評価額に大きく影響を与える点には注意が必要です。
純資産価額方式は特に小会社や、営業利益や配当があまり重視されないケースに適用されやすい特徴があります。
類似業種比準価額方式は、評価対象企業を上場している同業種の企業と比較することで株価を算定する方法です。具体的には、類似業種の平均株価と評価会社の配当額、利益額、純資産額を比準し、それぞれの比率を基に算定します。この算定式は次のようになります。
「類似業種平均株価 × (評価会社の配当額 / 類似業種の配当額 + 評価会社の利益 / 類似業種の利益 + 評価会社の純資産 / 類似業種の純資産) / 3 × 斟酌率 × 一株ネット資本金」
斟酌率は、会社規模に応じて調整され、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5とされています。この方式は、業種や規模の基準に合致する他社のデータを参考にするため、業界の標準的な評価を反映しやすい点が特徴です。
類似業種比準価額方式は、特に業界内での競争にさらされる中会社や大会社で用いられることが多いですが、適切な類似企業を選定する難しさや、業績や配当の変動が評価に大きく影響を与える課題もあります。
配当還元方式は、自社株の評価を「将来的に得られる配当」を基に算出する方法です。この方式では自社株の保有による収益性に着目し、継続的に配当を受け取る権利の価値を定めます。このため、特に「支配権を持たない同族株主」に対して適用されることが一般的です。
計算は「直前の配当金額 ÷ 政府が定める還元利回り(現在は5%など)」で行われます。たとえば、株式1株あたりの配当金が500円の場合、この方式での評価額は500円 ÷ 0.05 = 10,000円となります。
配当還元方式は、支配権が関与しないケースや、配当が安定している非上場の中小企業で魅力的な評価方法となります。ただし、配当を実施していない企業ではこの方式を採用できない点には注意が必要です。また、方法の性質上、あまり高額にはならないため、会社の資産価値が高くても低く評価されることがあります。
自社株の評価額は、会社が保有している総資産と負債の状況に大きく影響されます。純資産価額方式を用いる場合、会社が所有する資産の帳簿価額と時価の差額が算定に反映されます。例えば、総資産が増えれば評価額も自然と高くなりますが、負債が多い場合はその分評価額が低くなる傾向があります。そのため、純資産を適切に把握することが重要です。相続や事業承継の場面では、この財務状況を整理し、不必要な負債を削減することで、評価額を適切に管理できる可能性があります。
会社が保有している資産には、帳簿上の価額に比べて時価が高い場合、いわゆる「含み益」が生じます。この含み益が自社株の評価に反映されることで、株価が上昇し、結果的に相続税負担が増す可能性があります。例えば、不動産や有価証券など時価評価が必要な資産がある場合、高い評価額が算出されるため、相続税の負担が重くなることがあります。これを回避するためには、資産のポートフォリオを見直すことや、評価時期を調整することなどの対策を検討することが重要です。
上場株式と異なり、非上場株式の評価方法は会社の規模によって大きく異なります。たとえば、大会社の場合は主に類似業種比準価額方式が適用されますが、中会社や小会社では純資産価額方式またはそれらの併用が採用されます。また、配当還元方式は支配権を有していない少数株主に適用されるケースが多いです。事業承継や相続時の自社株評価においては、業績や従業員数、取引規模に応じた適切な方法を選択することが重要です。このプロセスでの誤りが評価額に大きな影響を与えるため、税理士などの専門家に依頼することが勧められます。
自社株評価を低く抑えるためには、純資産の圧縮が有効な手段の一つです。純資産価額方式では、会社の純資産額が評価額に直結します。そのため、純資産を適切に調整することが評価対策として重要です。具体的には、不動産や有形固定資産の購入で資産を減少させたり、不要なキャッシュを流動負債として計上することで純資産を圧縮できます。また、会社内部に留保されている利益を役員退職金や特別配当として外部に支出することで、純資産価額を減少させることも一つの方法です。
ただし、このような純資産圧縮には、相続や事業承継がスムーズに進むよう計画的に実施することが必要です。例えば、利益の処分方法や資産の購入計画を誤ると、逆に会社運営に支障をきたす可能性もあるため、税理士などの専門家と相談しながら進めるのが良いでしょう。
役員報酬や配当の調整も、自社株の評価額を低減させる上で効果的な手段です。純資産価額方式や類似業種比準価額方式では、配当金や利益の水準が評価に反映されるため、これらを適切に管理することで評価額への影響を緩和できます。
例えば、役員報酬を増額することにより、会社の利益が圧縮され、自社株の評価額を引き下げることが可能です。また、特別配当を実施して内部留保を減少させることも、自社株評価の低減につながります。ただし、役員報酬の増額や配当金の支給は、会社運営や資金繰りに影響を与えるため、無理のない範囲で行うことが重要です。
このような調整を行う際には、税制や法律に基づいた適切な方法を採用することが求められます。不自然な高額報酬や非現実的な配当金の設定を行うと、税務調査などのリスクが発生する可能性があるため、注意が必要です。
早期相続対策を講じることで、自社株評価額を引き下げることも可能です。時間的な余裕を持って対策を行うことにより、評価額に与える影響を計画的にコントロールできます。たとえば、生前贈与を活用して株式を分散させる方法があります。これにより、贈与税の基礎控除枠を活用しつつ、自社株の所有割合を調整できます。
また、事業承継税制の特例を活用することも検討すべきです。この税制では、一定の要件を満たす場合、自社株相続税評価額の全額または一部を納税猶予することが可能となります。これにより、相続人の納税負担を大幅に軽減することができます。
さらに、早期に対策を行うことで、会社の純資産価額や利益剰余金に直接的な影響を与えるため、自社株評価額の上昇を抑えることが期待できます。こうした早期対策を成功させるためには、自社株の評価方法や法律、税務に精通した専門家のサポートを受けることが大変重要です。
近年の税制改正により、相続時における自社株評価の方法や基準が見直されるケースが増加しています。特に「事業承継税制」の改正は、中小企業の事業承継を促進するための重要な柱となっています。この税制では、後継者が取得する自社株式について一定の条件を満たす場合に、相続税や贈与税の納税猶予が適用される仕組みが存在します。しかし、自社株相続税評価額や非上場株の算定基準の見直しにより、条件を満たす企業は細かいチェックが必要となり、税理士などの専門家の知識が不可欠です。また、税制改正に伴い、中小企業の規模や業績、純資産価額の変動が計算方式の選択や評価結果に大きく影響することになりそうです。
中小企業における事業承継では、自社株の評価をめぐる課題が多く見られます。特に、非上場株式の評価は時価が存在しないため、純資産価額方式や類似業種比準価額方式などの方法を用いて算定する必要があります。これには相続税の負担がどの程度発生するのかを適切に把握することが重要です。しかし、自社株は上場株式と比べて流動性が低いため、相続税の納税資金をどのように確保するのかという課題にも直面します。事例によっては、評価額を引き下げるための純資産の圧縮や役員報酬・配当の調整、さらには早期の相続対策が求められます。これらの対策を適切に行うことで、事業承継に伴う負担を軽減し、円滑な事業の引き継ぎが可能となります。
自社株評価は非常に複雑で専門性の高い分野であるため、相続や事業承継を円滑に行うためには税理士や公認会計士といった専門家に依頼することをお勧めします。専門家を選ぶ際には、自社の規模や業種に詳しい経験豊富な人物を選ぶことがポイントです。特に相続税や贈与税の計算に強い税理士であれば、非上場株式の評価方法や相続時の自社株評価に関する適切なアドバイスを受けることができます。また、税制改正の影響を踏まえて最新の情報を常に把握している専門家を選ぶことで、より正確で有利な評価を実現することができます。依頼する際には、具体的な財務データや経営状態を提供し、明確な合意のもとで進めるのが成功のカギです。